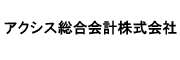I.中小企業も各種減税制度を活用しましょう
先日、トヨタ自動車の社長が「やっと法人税を払うことができる」といった事が話題になりました。
年間売り上げ高が25兆円を超え営業利益も2兆円を超える巨大企業なのになぜ?と思われた方も多い
と思います。もちろん、天下のトヨタが脱税をするわけはないので、合法的に納税を回避してきたので
しょう。
まず第一に法人税には欠損金の繰越控除という制度があります。赤字を出した場合にその赤字を次年度
以降の黒字と相殺できるという制度です。
トヨタ自動車は2009年に5604億円の赤字を出しているので、それを2010年以降の黒字と相
殺していると考えられます。しかし、トヨタ社は2010年以降毎年巨額の利益を出しているのでこれ
だけでは説明はつきません。
次に考えられるのは連結納税制度です。連結納税制度は法人税の課税にあたって企業グループ内の赤字
を合算し、税額を減らす制度です。親会社が黒字でも、赤字の子会社があれば、その赤字額を親会社の
黒字額から差し引けます。
法人税の課税対象となる利益が少なくなり、納税額を減らすことができます。
さらに研究開発税制や外国税額控除など各種減税制度を利用する事で法人税を減らすことができます。
研究開発税制は試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の
法人税額から控除することを認めるものです。また外国税額控除は外国で納付した外国税額を一定の範
囲で税額から控除する仕組みをいいます。
さらに日本親会社が外国子会社から受ける配当は、その配当(源泉税控除前)の95%が益金不算入と
されるようになりました。
トヨタはこのようにさまざまな税制度を利用した結果日本国内では5年間法人税を納めることなくきま
した。
一方国内の99%をしめる中小企業では、少ない利益の中からなんとか税金を支払っているところも少
なくありません。
各種の税金の減税制度はもともと政治献金を多く出している大企業からの要望でできたものも少なくな
いのですが、中小企業でも使える減税制度もいろいろとあります。
平成25年度から始まった所得拡大促進税制、生産性向上設備投資促進税制などは適用できる企業も多
いと思いますので大企業のように、せっかくの減税制度を活用してもらえればと思います。
なお、各税制にはいろいろな適用要件がありますので詳細は税務署や税理士にお問い合わせください。
II.相続税が身近な存在に
ブリュッセルで開催されたG7では、ロシア並びに中国への対応をめぐって各国首脳の本音と建前が交
錯する結果となったようです。ロシアについてはウクライナ情勢、また中国については海洋進出問題に
ついて、各国とも強い非難声明を出さなければならないというのが建前です。しかし、欧州はロシアか
らの天然ガスの安定供給の期待があり、クリミア編入についてはやむを得ないというのが本音のようで
すし、中国についても経済的な結びつきが強く、強い声明は出せないというのが本音のようです。我が
国もロシアに対しては北方領土問題の解決のためには同国との関係悪化は避けたいというのが本音だっ
たでしょう◆この報道と同じころ、欧州中央銀行=ECBがマイナス金利の導入を決定したことが伝え
られました。その効果については今後を注視しなければわかりませんが、インフレ率が低下しさらには
デフレ懸念さえあるとのことでこの決定になったことが報じられています。「デフレ先進国?」である
日本は、昨年4月にデフレ脱却に向けて本格的に始動し、現在その途上にあります。欧州債務危機が何
とか落ち着いたと思ったものの、まだまだ欧州経済は予断を許さないようです◆さて、最近何かと目に
するのが「相続税」という三文字です。その大きな理由は、来年から相続税の増税が決定していること
です。では、相続税の税収は年間いくらぐらいあるのでしょうか?財務省の資料によれば、平成24年
度の税収は約1.5兆円(贈与税を含みます)となっています。国の試算によれば、今回の増税によっ
て3千億円程度の税収増を見込んでいるようです。この金額が大きいのか小さいのかはよくわかりませ
んが、財政健全化に資するにはあまりに規模が小さすぎます。いずれにせよ、国民の財産が税金という
形で国に移転することだけは間違いありません◆ここからは個人的な意見です。まず、金額の多寡にか
かわらず国民の財産が国に移転するわけですから、その使途についてはさらに目を光らせる必要があり
ます。今回の改正ではバブル後の地価の下落と格差の固定化防止がその趣旨にうたわれていますが、格
差の固定化防止に着目すれば、そこに重点的な予算措置が講じられなければなりません。また、今回の
もっとも大きな改正点は、基礎控除額の引き下げと最高税率の引き上げです。基礎控除額の引き下げは
相続税が多くの国民にとって身近になったとも言い換えることができます◆相続税が身近な存在になっ
たことについては何とも言えませんが、今回の増税についてはやはり個人的には?なのです。デフレか
らの脱却ということと地価の上昇は少なからず関係はあるでしょうし、経済政策と税制とがうまくかみ
合っていない印象です。デフレからの脱却により、企業業績が良くなり、労働者賃金が上がるとともに
経済格差も是正され、株価も上昇するといった良いスパイラルが生まれることを税制が足を引っ張るこ
とになるのではないかと心配するのは杞憂でしょうか。国の経済成長にとって税制は非常に重要な役割
を果たしてきたということを忘れてはならないはずです。
III.2次産業主導の6次産業化
馬車道駅の近くを歩いているとき、ドーム型のビニールハウスが設営されているのを見かけました。
どこかで見たことがあるような気がして調べてみたところ、2011年の「横浜ビジネスグランプリ」のフ
ァイナルステージに出場していたベンチャー企業の「エアドーム式植物工場」だということがわかりま
した。
横浜市が推進している「横浜発次世代植物工場技術発信事業」の一環として、新市庁舎整備候補地に期
間限定で設置しているそうです。
円形のプールに渦巻状に浮かべられた野菜が成長に合わせて外周に移動することによって、植え替えが
不要になり面積あたりの収穫量も倍増するという設計が画期的で印象に残っていました。また、太陽光
を効率よく取り入れる素材や構造、コンピュータで水や空気の流れを制御して、農薬を使わずに安定し
た品質の野菜を作る等、最先端の技術を駆使しています。
横浜市はこのほかにもオフィスビルの1フロアでLEDの光で野菜を栽培する「LED菜園」の運営も
行っているそうです。
6次産業化といえば生産(1次産業)+加工(2次産業)+販売(3次産業)という計算式ですが、野
菜を工場で作るというのは生産の部分が2次産業なので、少し違った新しい形なのかもしれません。い
ずれにしても、農業人口の減少や人手不足、食料自給率の低下といった問題を解決していくことが期待
されていると思います。
(Webデザイナー)
IV.退職時の心構え
先日、インターネット上で、『新人がすぐ辞めないよう心構えを教えてやれと上司に言われたので、い
くつか伝えた中の一つとして「辞めると来年の住民税で死ぬから計画的に」と伝えた。』という書き込
みを目にしました。
確かに、会社を辞めるとなるとよく耳にするのがこの住民税の支払に関してです。私自身も最初に就職
した会社を退社する際、まず言われたのが、住民税の支払分だけは最初に確保しておきなさい、という
ことでした。
住民税は後払いになるので、入社1年目は徴収されません。なので、2年目になった時に手取りが少な
くなっていると感じたこともあるのではないでしょうか。
住民税は、課税される年度の前年の1月~12月までの1年間の所得を基準に税額が計算されます。サ
ラリーマンの場合、年末調整の時期に所得の証明書として発行される源泉徴収票と同じ内容が、給与支
払報告書として、勤務先から各住所地の市区町村に送られます。このデータをもとに住民税の金額が計
算されるため、失業期間中などで収入がなくても、住民税の支払義務が生じるのです。
ちなみに退職して、社会保険から国民健康保険に切り替える場合も、前年の給与等をベースに算定され
ることとなります。
退職は計画的に、というのは間違いがないようです。
(企業会計アドバイザー 米山 裕子)
V.良い意味での脱力感
サッカーのW杯ムード一色の中、今年もAKBグループの選抜総選挙が行われました。この日、なぜか
ひどい脱力感に襲われた私はさらなる脱力感を求めて?初めてこの総選挙のTV観戦?を行ったのでし
た。
今回は、過去連覇を果たしたメンバーがいないということから指原さんの連覇に注目が集まったようで
した。
3位までの発表が終わり、会場は大いに盛り上がります。2位の発表が終わり、1位は渡辺麻友さんに
決定しました。
その後は、恒例のスピーチとなるわけですが、今年の渡辺さんの意気込みは頼もしく立派なもので、い
よいよ、連覇どころか長期政権の予感さえうかがわせるものでした。
毎回さまざまなドラマが生まれるこのイベントですが、どういうわけか私にとってはほほえましく感じ
られるのです。それが良い意味での脱力感につながっているのだと思われます。
若い女の子たちが一生懸命頑張っている光景に勇気や力をもらう一方で、それぞれの個性が最も輝くの
がこのイベントの素晴らしいところではないでしょうか。
改めて彼女たちのステージでの衣装をよく見てみてください。一見同じように見えますが、一人ひとり
少しずつアレンジされているのがわかると思いますよ。
(覆面ライター 辛見 寿々丸)